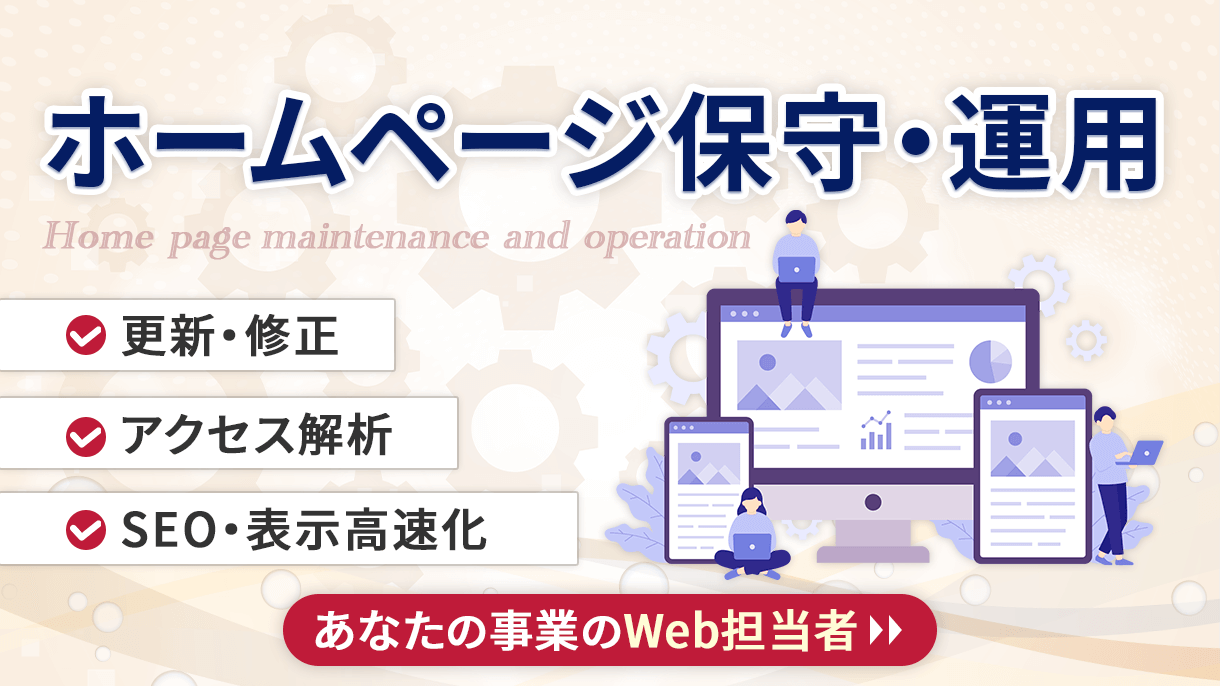Webサイトを作ったまま放置するとどうなるのか?保守・運用の重要性
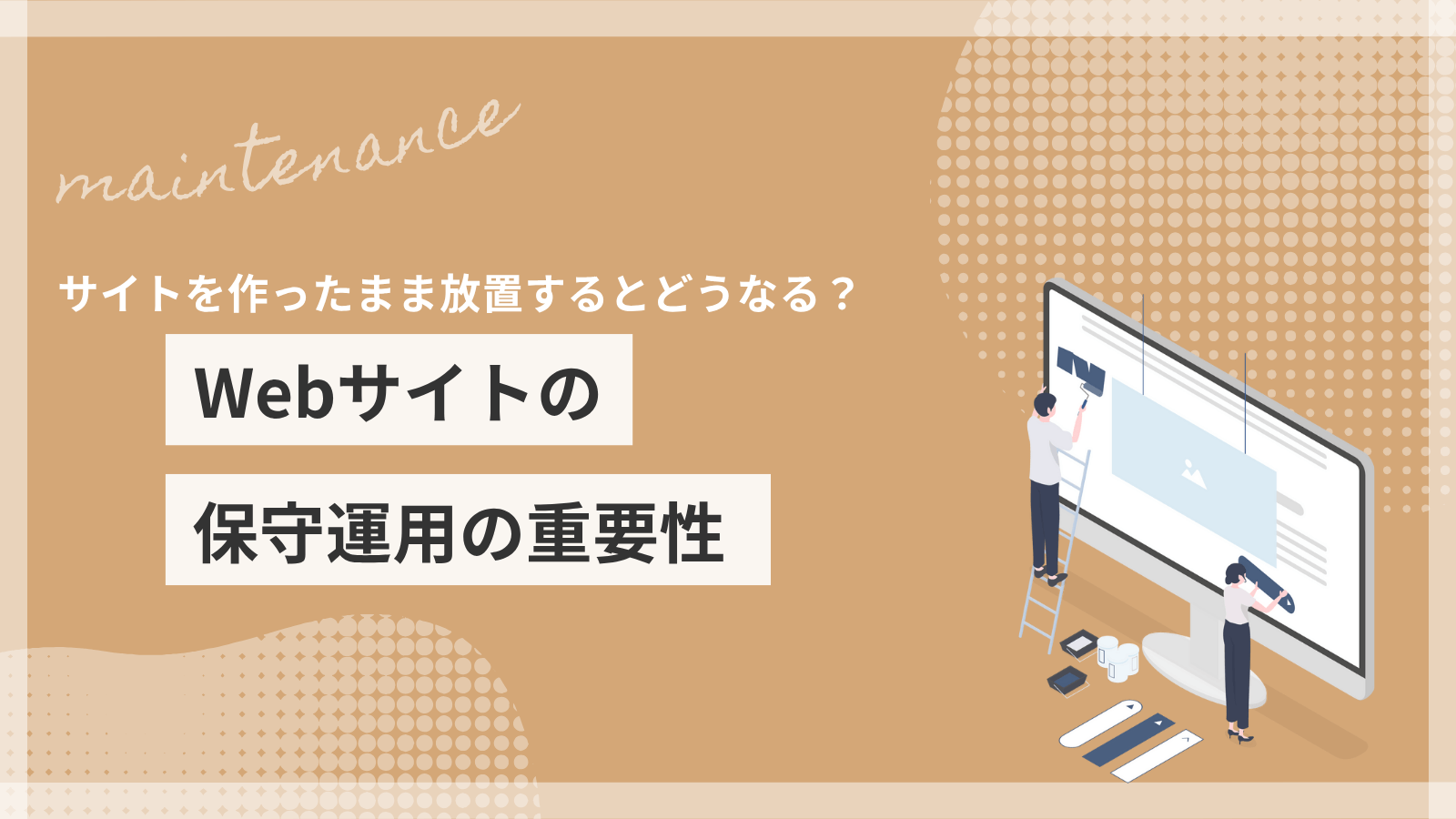
Webサイトは単なる情報発信の場ではなく、企業や店舗の顔となり、顧客との重要な接点となります。Co-Creationでは、コーポレートサイト・採用サイト・店舗ホームページ・オウンドメディアなど、様々なWebサイトの制作に携わってきましたが、常々感じるのは、Webサイトは「完成して公開したら終わり」ではない、ということです。むしろ、「完成して公開してからがスタート」であり、保守と運用という2つの重要なプロセスを通じて、サイトを「育てていく」必要があるのです。
この記事では、Webサイト、ひいては会社の事業を成長させるために不可欠な「保守運用」の重要性について、詳しく解説していきます。
Webサイトの「保守」とは?
Webサイトの「保守」とは、Webサイトが技術的に問題なく稼働し続けるためのメンテナンス活動全般を指します。いわば、Webサイトの健康を維持し、病気を未然に防ぎ、もしもの時は治療する、という「守り」の役割です。
「Webサイトの保守運用って聞くけど、具体的に何をしているのか分からない」という方もいらっしゃると思います。具体的には、以下のような内容が含まれます。(制作会社によって保守の内容は様々であり、あくまで一例です)
Webサイトの「保守」 ー 予防(未然に問題を防ぐ)
- ドメイン・サーバーの更新
- CMS(WordPressなど)やプラグインの定期的なアップデート
- データバックアップ
- セキュリティ対策
- 内部SEO対策
- サイト表示高速化対応
①ドメイン・サーバーの更新
Webサイトが表示されるための土台となるドメインやサーバーは、それぞれ契約期限があります。契約しているドメイン・サーバーの更新が滞ると、期限が切れたタイミングからWebサイトが表示されなくなり、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。そういった事態を未然に防ぎ、安定した稼働を維持します。
②CMS(WordPressなど)やプラグインの定期的なアップデート
WordPressなどのCMS本体や、利用しているテーマ、プラグインなどは定期的に機能改善や脆弱性への対応のためのアップデートが行われます。これらのバージョンアップ作業自体は一見簡単なことが多いのですが、CMS本体はアップデートしたものの、使用しているプラグインが最新のバージョンに対応しておらず、サイトに不具合が発生してしまうというケースも少なくありません。
新たなバージョンでは何が改善されるのか? バージョンアップをすることでサイトに何か影響は出ないか?など様々な観点から検討し、アップデート実施可否の判断をします。
③データバックアップ
Webサイトのデータは、システムトラブル、誤操作、サイバー攻撃など、予期せぬ事態によって失われる可能性があります。万が一に備え、Webサイト全体のデータを定期的に、かつ安全な外部ストレージサービスにバックアップします。これにより、万が一の際にも、迅速かつ正確にサイトを復旧させることが可能です。更新頻度が高いサイトほど、日々のバックアップがビジネス継続のための重要な「保険」になります。
④セキュリティ対策
Webサイトをサイバー攻撃から守るための多層的なセキュリティ対策です。SSL証明書の適切な運用と更新はもちろん、CMSへのログインURLの変更や画像認証の導入などを施すことで、不正アクセスや改ざんといったあらゆる脅威からWebサイトを保護します。
⑤内部SEO対策
Googleなどの検索エンジンで上位表示を目指す上で、Webサイトの内部構造は非常に重要です。基本的に制作時にしっかり施されるものですが、納品後にお客様側でコンテンツを更新していく場合、画像のAltタグの設定漏れや見出しの付け方の誤りなど、技術的なSEO対策の抜け漏れが出る可能性が高くなります。保守では、こうした技術的なSEO対策の不備を修正し、検索エンジンがサイトの内容を正確に理解し、高く評価できるようサポートします。
⑥サイト表示高速化対応
Webサイトの表示速度は、ユーザー体験と検索エンジン評価の両方に影響します。こちらも制作時に考慮されますが、納品後にお客様側でコンテンツを更新する場合、容量の大きな画像をリサイズ・圧縮せずにアップロードしてしまうと、サイトが重くなり、SEO対策が崩れる可能性が高くなります。保守では、こうしたパフォーマンス低下の原因を特定し、画像を最適化するなど、様々なアプローチでサイトの表示速度を高速化します。これにより、ユーザーはストレスなくサイトを利用でき、検索エンジンからの評価向上にも繋がります。
Webサイトの「保守」 ー 是正(発生した問題を特定し修正する)
- サイトの表示崩れチェック
- サイトの修正・更新作業
- 新しい端末やブラウザでの表示互換性の確認
①サイトの表示崩れチェック
サイトのデザインやレイアウトが意図せず崩れていないかを定期的に確認します。CMSやプラグインのアップデート、サーバー環境の変更、新しい端末やブラウザの登場などによって、サイトの一部が表示されなくなったり、レイアウトが崩れてしまったりすることがあります。こうした表示の不具合は、ユーザーに不信感を与え、離脱に繋がるため、チェックは欠かせません。
Webサイトの「運用」とは?
一方で「運用」は、ビジネスの目標達成に向けて、サイトをユーザーにとって魅力的で効果的なツールとして改善していく・育てていくための活動です。単にサイトが動いているだけでなく、そこから成果を生み出し、価値を最大化していく「攻め」の役割を担います。
「運用」は、適切な「保守」ができていてこそ成り立つものですので、運用よりも先にしっかりとした保守体制を構築することが重要だといえます。
具体的には、以下のような内容が含まれます。
- パフォーマンスの最適化と改善
- コンテンツの更新
- マーケティング・プロモーションとの連携
①パフォーマンスの最適化と改善
Google Analyticsなどのツールを用いて、Webサイトへのアクセス状況、ユーザー行動、コンバージョン率などを詳細に分析します。その分析結果に基づき、サイトの改善点を見つけ出し、ユーザー体験向上、コンバージョン率の改善、SEOなどの施策を立案・実行します。
②コンテンツの更新
Webサイトの情報は、常に新鮮で最新の状態を保つことが非常に重要です。新製品のリリース、キャンペーン情報の告知、サービス内容の変更、ブログ記事の追加など、ビジネスの変化や市場のニーズに合わせて、Webサイトのコンテンツを適時更新・追加していきます。情報が古いままだと、ユーザーは企業の活動状況を把握できず、信頼性にも影響が出かねません。定期的なコンテンツ更新は、ユーザーへの価値提供だけでなく、SEOの観点からも重要です。
③マーケティング・プロモーションとの連携
Webサイトは、単体で存在しているわけではなく、企業(店舗)のマーケティング戦略全体の中で、SNS・メルマガ・広告など、他のプロモーション活動と連携することで、その効果を最大限に引き出すことができます。例えば、SNSでのキャンペーンと連動したLPの制作、メールマガジンからの流入を促すコンテンツの最適化などを行います。Webサイトがマーケティングの中心となるよう、戦略的な視点を持って運用します。
このように、「保守」が技術的な側面を維持する役割であるのに対し、「運用」はより戦略的にWebサイトを運用し、ビジネス成果に結びつけるための幅広い活動を指します。これら二つが適切に連携することで、Webサイトは最大の効果を発揮できるのです。
保守運用をせずWebサイトを放置することで起こるリスク
繰り返しになりますが、「Webサイトは作って終わり」ではありません。むしろ、公開後の保守運用こそが、サイトの健全な稼働とビジネス成果の維持に不可欠です。適切な保守運用を怠ると、サイトに以下のような深刻な問題が発生する可能性があります。
サイト表示の不具合やエラー
Webサイトの表示は、サーバー、ドメイン、SSL証明書、そしてサイト自体のコードなど、多くの要素が連携して成り立っています。これらのいずれかに問題が生じると、サイトが表示されなくなったり、デザインが崩れたり、機能が正常に動作しなくなることがあります。
例えば、ドメインの更新忘れによってサイトが表示されなくなったり、SSL証明書の期限切れで「このサイトは安全ではありません」という警告が表示されたりします。また、新しいブラウザやデバイスの登場、Webサイトのコードの古さなどが原因で、サイトのデザインが突然崩れたり、問い合わせフォームなどの機能が正常に動作しなくなったりすることもあります。
これにより、サイトのイメージが低下するだけではなく、ユーザーは目的の情報にたどり着けなくなったり、購入や問い合わせといった行動ができなくなったりします。結果として、ユーザー体験が著しく損なわれ、サイトからの離脱率が増加し、貴重なビジネスチャンスを逃してしまうことに繋がりかねません。
セキュリティリスクの増大
Webサイトを構成するCMS(WordPressなど)や各種ソフトウェアには、常に新たな脆弱性が発見されています。これらを定期的にアップデートせずに放置すると、不正アクセス、情報漏洩、サイト改ざんなどのサイバー攻撃の格好の標的となります。一度攻撃を受けてしまえば、復旧にかかる費用や時間だけでなく、企業の信頼失墜という取り返しのつかないダメージを負うことになります。
検索エンジンからの評価低下
Googleをはじめとする検索エンジンは定期的に更新されるサイトを高く評価します。これは「Freshness(鮮度)」と呼ばれる評価要素の一つです。長期間更新のないサイトや情報が古くなったサイトは検索エンジンから「低品質」と判断され、検索結果の上位に表示されにくくなります。これも自然検索からのアクセスが減少し、新規顧客獲得の機会を失うとともに、信頼性やブランドイメージを大きく損ない、顧客からの信頼回復に多大な労力を要することになります。
「自分たちで保守運用」の落とし穴:実際にあった失敗事例
「Webサイトの保守運用なんて、自分たちでもできるだろう」と考えて、専門知識がないまま自社で対応しようとし、結果として大きな損失を被ってしまうケースもあります。ここでは、実際にあった失敗事例を2つご紹介します。
ケース①:公開後2ヶ月後にフォームからの問い合わせが届いていないことが発覚
とある中小企業で、公開後2ヶ月程経った頃に、お客様より「問い合わせをしたが返事がない」との電話があり、調査をした結果、問い合わせフォームからのメールが正常に管理者に届いていないことが発覚。サイト制作時にドメインを新たに取得してメールアドレスも併せて設定、送受信テストも行っていたのですが、納品後にお客様側でメールサーバーからメーラー(OutlookやGmailなどのメールソフト)への受信設定を独自でいじってしまったことが原因でした。
ケース②:容量の大きい画像をたくさん入れたことによる表示の低速化
公開後にお客様側でブログを更新していく際に、容量の大きな画像をリサイズ・圧縮せずにどんどんサイトにアップロードしていったことにより、サイトが重くなってしまったケースもありました。また、そのアップロードした画像にaltタグがついていなかったことで、内部SEO対策は崩れてしまっていました。
いずれのケースも、事前に保守管理のお話をさせていただいたり、画像のリサイズ・圧縮の重要性については、納品時の動画マニュアル等でご説明をしていたのですが、保守管理を自社で行うご意向の会社様でした。
画像のaltタグ、リサイズ・圧縮については、下記の記事でもその重要性をご紹介しています。
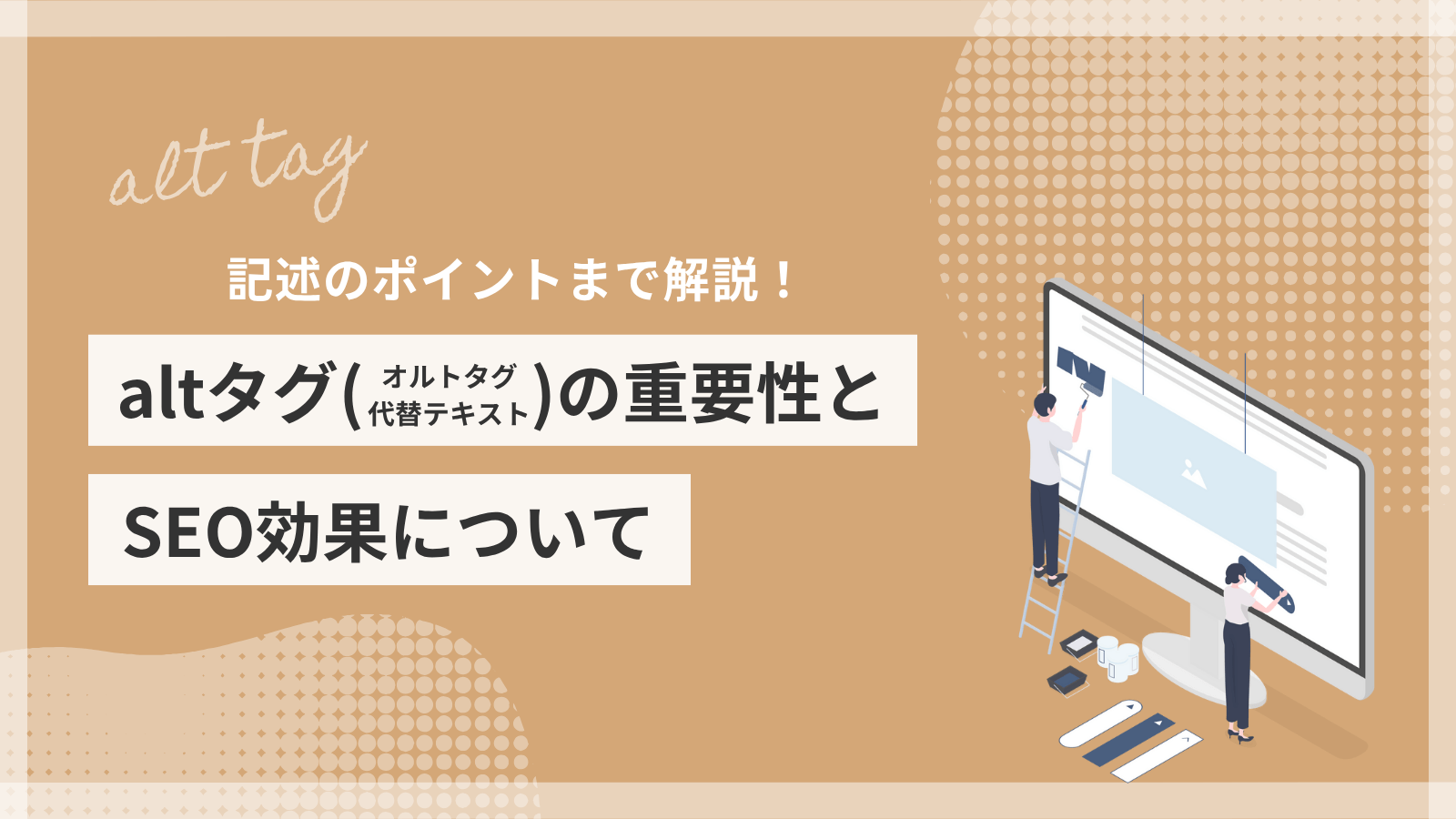
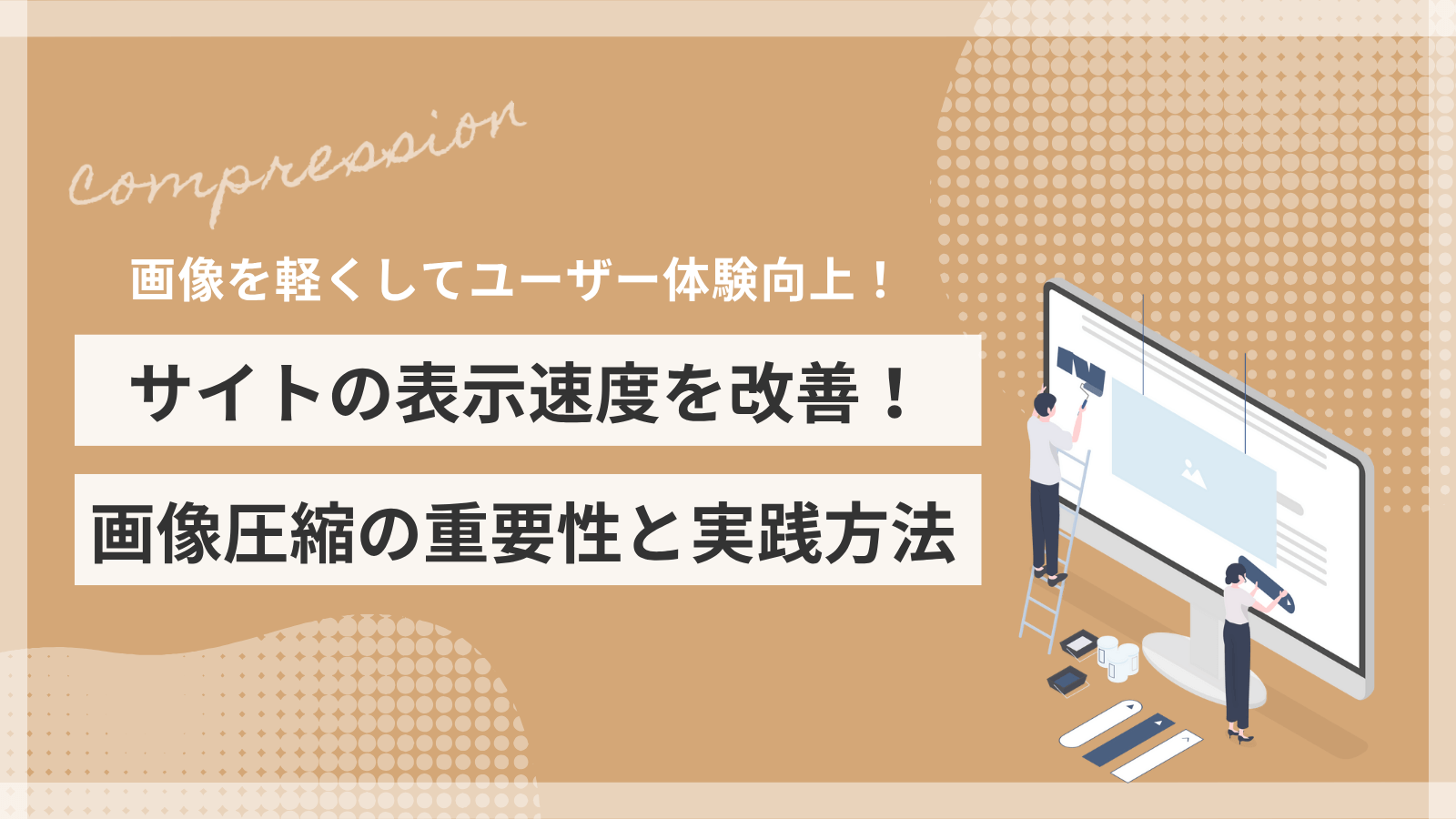
保守運用の重要性
Webサイトの保守管理は、不動産で例えると「一戸建て」か「集合住宅」の違いに似ています。一戸建ては庭の手入れやトラブル対応などはすべて自分たちでやる必要があります。一方で集合住宅は、例えば管理費や修繕積立金を支払っていれば、清掃やトラブルは管理会社が代行してくれます。
自社でWebサイトの保守運用を行うことは、潜在的なリスクや責任を負う可能性がある一方で、制作会社やプロに保守運用を委託することで、多くの手間とリスクから解放されます。
Co-Creationでは、今回ご紹介した「保守」と「運用」の両面から、ビジネス成果に貢献する保守運用サービスを提供していますが、Webサイトに万が一のことが起こった場合に備え、また起こることを未然に防ぐために、実際にお客様の9割以上が弊社の保守運用プランをご利用いただいています。
せっかく費用と時間をかけて制作した大切なWebサイト。それを常に安全で最適な状態に保ち、先の事例のようなリスクを回避するためには、専門知識を持つプロのサポートが不可欠です。保守運用は単なる経費ではなく、サイトを「育てていく」ための未来への投資だと考えてみませんか?
弊社の保守運用サービスの詳細は、下記の記事でご紹介しております。ご覧ください。